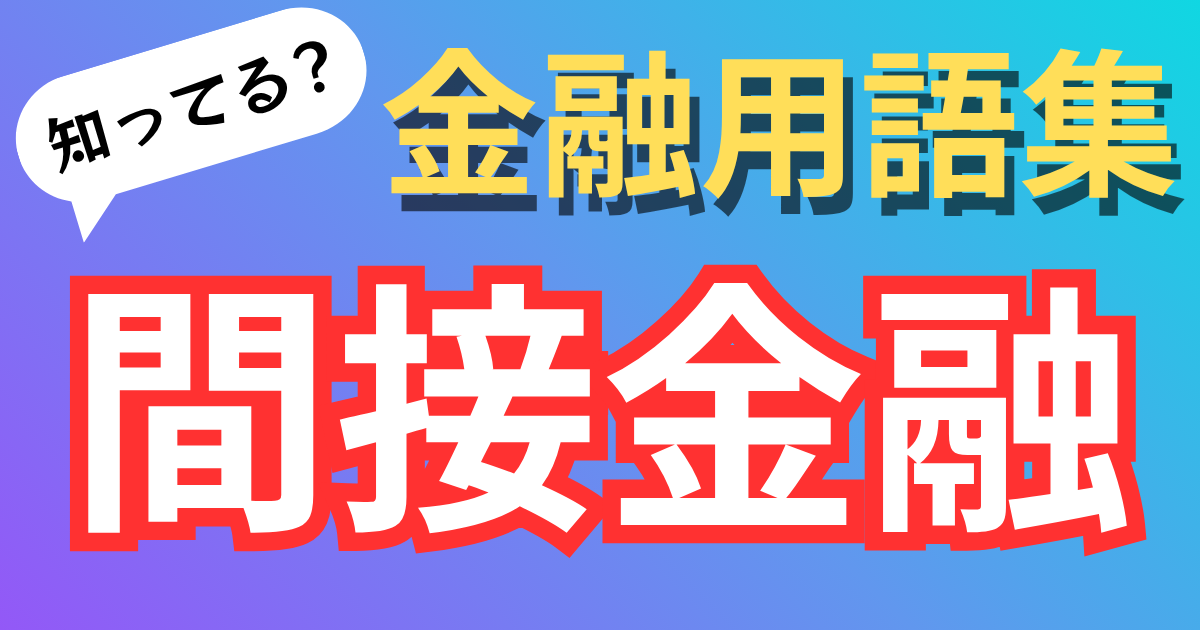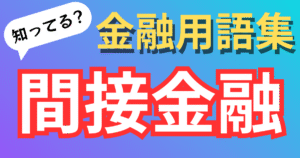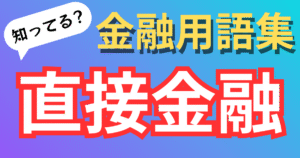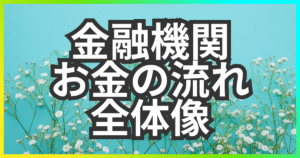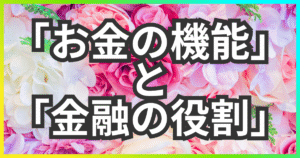・金融用語:間接金融
・読み方:「かんせつきんゆう」
・用語解説:
資金が必要な企業や個人(資金需要者)と、お金を預けたい家計など(資金供給者)のあいだを、銀行や信用金庫といった金融機関が“仲介”して資金を融通する仕組み。預金者から集めた資金を、金融機関が審査・管理のうえで貸出し、利息差(預金金利と貸出金利の差)を収益とする。銀行が信用リスクや返済管理を引き受けるため、預金者は安全性の高い元本保証商品を利用でき、企業は審査を通じて比較的安定的に資金を得られるメリットがある。また金融機関は多数の小口預金をまとめて長期融資に転換し、満期や規模のミスマッチを吸収する「期間変換」「規模変換」機能も果たす。一方、仲介コストが発生するぶん資金コストは直接金融より高くなりがちで、過度に銀行依存が進むと企業の成長資金調達が制約されるとの指摘もある。日本では戦後長らく主流だったが、資本市場の整備が進むにつれて直接金融とのバランスが重視されている。